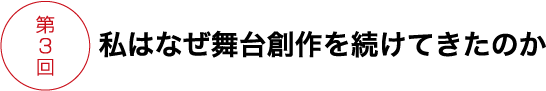小池 博史
(こいけ・ひろし / KOIKE・HIROSHI)

演出家。茨城県日立市出身。一橋大学卒業後、TVディレクターを経て82年パフォーミングアーツグループ『パパ・タラフマラ』 を設立。以降、全作品の作・演出・振付を手掛け、国際的に高い評価を確立。3.11を機に翌2012年パパ・タラフマラ解散後、『小池博史ブリッジプロジェクト』発足。創造性を核に教育・発信・創作を三本柱とした連携プロジェクトとして現在までに8作品を創作。国際交流基金特定寄付金審議委員(2004年~2011年)などを歴任。現在「舞台芸術論」(仮題)の出版準備中。
小池博史ブリッジプロジェクト
http://kikh.com
そこで、「小池博史ブリッジプロジェクト」では、創造性を核に置き、創作、教育、発信という三つの柱を作った。教育としては「パパ・タラフマラ付属研究所」として1994年から実施してきており、その小さな塾型の学校は継続するとして、それ以上にさまざまな市民とのワークショップなどを意識的に展開し、一般市民に対して大きく開かれた形を模索せねばならないと感じていた。発信は出版の形を含めて、いろいろな手立てを講じつつ、言葉として示していく必要があった。どんなものでも情報に換言できてこそ価値を持つという幻想がまとい付いた情報化社会では、わかりやすいものほど飛びつき、飛びつかれやすい。そうした人々に対しての方法を提示する必要はあった。だが本来、芸術はそんなもんじゃない。芸術は深層に呼びかける力がある代わりに、決してわかりやすいとは限らない。得てして本物の芸術作品は瞬間的にはわかりにくい作品の方がずっと多い。けれど、それは圧倒的力で迫ってくる。しかし「圧倒する力」は見る者、聴く者にとって明快な言葉にはなかなか換言しにくい。だから私自身、自ら意識して語る必要があった。わからないやつは放っておけという態度ではなく、もしわからないならばわかるための手立てを用意しましょうという態度に私自身を変えなければならなかった。
日本は、文化芸術面での民度は決して高くはない。高いと思いたいのが日本人の心情だろうが、明治以降の大転換によって、政治、軍事、社会制度はもとより、文化そのものも大きく変えられてしまい、それによって私たち日本人の感覚そのものにも狂いが生じてそのままとなった。芸術の見方、感じ方もまた狂ったまま維持されてきたのが現状であろう。「わかりやすさを求める」のはその典型例だ。江戸時代までの日本人はきわめて抽象的な形や音を自然に取り込める土壌を持っていたが、かなり薄れた。そして民度自体が狂ったまま低下した。欧米はもとよりインドネシアやインドと比べてもまったく高くないどころか、かなり低いと言わざるを得ないのが現状だ。それは自分自身で作品を見る目を持たないがため、マスに同調するのが良いことだと思い込んでいる人が多い状況として現れている。
たとえばすでに亡くなってしまった、日本で大人気のピナ・バウシュ。決して彼女を非難するために書くのではない。彼女には良質の作品が多数ある。だがそうではない作品もある。ところがどうであっても彼女の作品であれば日本ではスタンディングオベーションとなる。最初からスタンディングと決まっている。私は東京とニューヨークで同じ作品を見た経験があり、東京の観客は大変熱狂的に迎え入れていたが、ニューヨークでは、かなりの人が途中退席していた。これはなにを意味するか? 言わずもがなだ。最初から日本では評価は決まっており、その評価に従ってしかモノを見る尺度がない、すなわち自身で見る力が弱いことを示している。

こうして創作活動としては、人間ではない視点、すなわち動物、死者、自然の視点から描いた宮沢賢治のシリーズを3作品ほど創作し、神々の話に始まり破滅へと至ってしまうインドの大叙事詩、「マハーバーラタ」シリーズとしてすでにアジア各地で4作品を制作し、ツアー化してきている。これらはすべて時代、国境、人種、宗教……等々に橋をかけるために、古典のアーティストを多く入れ、アジアのアーティストで構成し、と、新たなる方法を探っているなかでの創作だ。特に「マハーバーラタ」は2020年まで続くプロジェクトだが、一方向に向かって直線的に進む西洋型思考ではなく、アジア型の循環思想を基盤とした哲学こそが今後は核にならざるを得ないとの思いから、毎年7か国のアジアのアーティストが混じり合って、調和型社会の可能性を舞台を使い制作している。
また、「賢治シリーズ」を終えたので、今年から「世界シリーズ」を開始した。その第一弾として「世界会議」を創作。今、私たちが向かい合わなければならないのは「この場」であり「現在」であると同時に、「世界の隅々」であり、「遠い過去と遠い未来」、「近い過去と近い未来」を等価に見据える意識だと考えるからだ。「この地」と「現在」だけを見ていれば、暗澹たる気持ちにしかならない。加えて今という時代は、遠い未来には目をつぶり、目の前だけを見て活動する人の方が間違いなく出世しやすく、成功者になりやすい社会である。政治家はどこを向いて仕事しているのか、と思えるような人ばかりとなった。こんな状態では私たちは生きられない。よしんば、私は生き延びられても、百年後の世界はなくなってしまう可能性が高い。「遠い未来」と「世界の隅々」を見据えれば、どうあっても、今必死になって考えを改めなければヒトの未来自体が消滅するだろう。
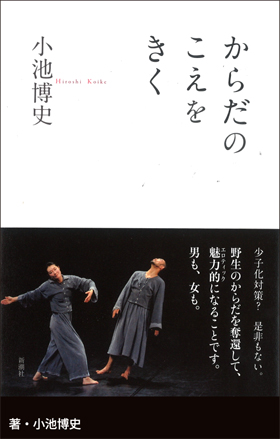 さて本題に戻ろう。
さて本題に戻ろう。
みなさん、舞台芸術のメリットとは何であるか? 考えて欲しい。メディアとしてはとても小さい。将来に、形として残らない。よって後で評価されることはない。しかし芸術である限り、遠い未来を見据えるのは必然であろう。ましてや日本人は民度の高い国民にはなっていない。とするなら、なんらメリットはないではないか? 映像は残り、再上映はやろうと思えば可能だ。音楽も美術も形として残せる。複製芸術としてかなりの程度、実際に近づけることが可能なメディアだ。一方、舞台芸術はあまりになにも残らず、複製も効かない。これではメディアとして弱すぎる。
さて、本当にそうだろうか。
私はこれほど可能性の高いメディアはないと思い、35年間に渡り制作し続けてきた。確かにメディアとしては小さく、記録程度しか映像としてはとどめられない。映像に残った舞台は記録としての価値はあっても、実際の舞台とはかけ離れた別物である。理由は明快だ。そこには空間がなく、同時間軸には観客は存在しない、つまりライブではないからである。
ライブであることがそんなに素晴らしいのか、という疑問が出てくると思う。音楽であれば緻密な録音技術があって、そのライブ感を記録メディアに残すのは可能だ。もちろん映像としてではない。音楽は音が9割と言ってよいメディアだ。しかし舞台芸術は視覚芸術であり聴覚芸術である。私たちの脳内では出演者の表情を読み取りつつ全体の動きを認識するのは可能だが、映像メディアではその両方を同時には収められない。音にしてもあらゆる音を正確に記録するのはきわめて難しい。ましてや舞台作品は観客との交感によって成り立つメディアである。劇場空間を盛り上げるに観客の役割は欠かせず、絶大だ。そしてそこには生の身体があるから、ダイレクトに伝わってくる。舞台空間は生命空間なのだ。
さらに言えば、舞台芸術作品は、空間・時間・身体という三つの大きな要素によって成り立つメディアである。これはなにを意味するか? 限界がなく、どこまでも膨らみ得る可能性を持つことに繋がる。すでにやり尽くされているという人がいるが、一体なにを見ているのか?と思う。空間、時間、身体を操作できれば縦横に可能性が広がっていく。その限界値ははるか彼方にあり、私にはまったく見えない。
この話を詳しく書き出すと、いくらでも書けてしまうからこの程度でとどめておこう。
身体に強烈に染み込む作品を残せば、人の記憶の奥底に留まって、ゆっくりと人の成長を促すだろう。芸術家の役割はその深層の意識に訴えかけるところにある。芸術が金儲けや名声を得るための手段と考える人たちは決して少なくはなく、寂しさを感じないわけではない。が、それはそれ。
まず、私は次の作品をどう変えていけるか、である。
[ガリバー&スウィフト][WD][パンク・ドンキホーテ]
FLYER : アートディレクション 葛西薫
2017年8月の国際共同制作作品「戦いは終わった―マハーバーラタより」は、クラウドファンディングを実施しています。6月からチェンマイにて制作、公演、その後バンコク、東京とツアーを予定していますが、なにぶん、資金不足に陥っており対応に迫られております。ご協力いただければとても助かります。
オリジナルグッズ等、さまざまな特典がありますので、ぜひにご協力のほどを。
詳しくはこちら : https://motion-gallery.net/projects/koikewiomb4